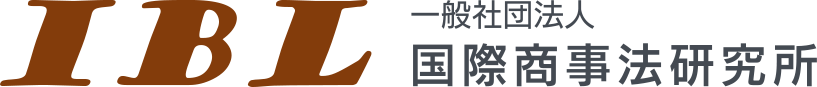2025年02月18日公開
中国企業法務の軌跡(8)~労働争議(前半)~
J&Cドリームアソシエイツ 大澤頼人*1
1. 工場移転
ある日本のメーカー企業(ここではA社といいます)は中国子会社(ここではB社といいます)の業績が悪く連結決算にダメージがありB社を切り離したいが、世間でよく言う会社を解散して清算するという方法は取りたくないと考えています。
A社はもともと日本に工場をもっていましたが、国内のコストの増加に伴い利益が出なくなったので1990年半ばに上海市の郊外に工場建物を借りてB社を設立し生産拠点を中国に移しました。その当時の日本の製造業の典型的な中国進出事例です。進出当時は上海の郊外に工場を借りました。1990年代の上海市は今では想像できないくらい地味な都市でした。私もその当時、上海市に出張したことがありますが、今では有名な外灘の夜景や浦東の高層ビル群もなく、夜は真っ暗で唯一テレビ塔だけが明るく建っているだけの街で、夜に街を歩くと人とぶつかるような暗さでした。上海市の郊外は外資系企業や地元の工場が林立していました。今では再開発されてその当時の工場はひとつもありません。
B社が中国に進出した当時は社会主義市場経済政策が始まったばかりで外資系企業には様々な優遇措置があり、物価や人件費も安く、B社は実績をどんどん上げて成長しましたが、上海市の成長とともに工場移転を強いられるようになりました。
B社には設立当時から日本人駐在員をサポートしていた副総経理の中国人従業員がいました。彼の父親はある地方都市(ここではX市といいます)の共産党委員会の委員でした。その地方都市は名前こそ市がついていますが実際は市より下級の県レベルの規模の都市で財政状況は決して豊かではありませんでしたので外資の誘致に必死になっていました。副総経理は上海市の工場を移転しなければならないB社をX市に移転させてはどうかと提案しました。
中国の地方都市の財源の中心は国有地の払下げです(その結果、最近のように住宅不況になると地方都市の財政は急激に悪化します)。X市には地元企業が解散したあとの工場建物があり、工場が建っていた国有地の使用権はX市政府が買い戻していました。前の所有者が二つの鎮政府から借り受けた二つの工場建物も残っているようで、その国有地の使用権の払下げを受けるときは鎮政府の建物を借りるという付帯条件がついていました。副総経理の人脈で結びついた地方政府の思惑はB社の窮状を救いました。
2000年に入ってB社はX市から国有地の使用権の払下げを受け、上海市から移転しました。上海市からの移転補償金を移転費用に充てました。上海市の工場は閉鎖し従業員との雇用契約は中途解約しました。労働契約の中途解約は上海市政府による強制移転によるものでB社の都合ではありませんので経済補償金(日本でいう退職金)を支払う必要がありません。移転先の工場をマザー工場にし、二つの鎮政府が所有する二つの工場建物は分公司工場としました(分公司には法人格はありません)。上海市の旧工場に比べると3倍の規模ですが生産量は増えていたので三つの工場を持つことに問題はありませんでした。従業員は全て地元の住民で、いわゆる農村からの出稼ぎ労働者はいませんでした。従業員数は最盛期のときで工場が約1,000名、管理部門が約20名いました。
*1) 2013年まで伊藤ハム法務部長、その後J&Cドリームアソシエイツを設立し代表。2002年伊藤ハム中国の一般代表。2013年まで伊藤ハムの中国の董事、監事。2008年~2011年まで上海交通大学法学院客員教授、2017年~2022年中国哈爾濱市仲裁委員会委員、2006年~2023年同志社大学法学研究科非常勤講師、2017年立教大学法学部非常勤講師、2019年~2023年株式会社大泉製作所社外監査役。中国進出、事業再編、ガバナンス、コンプライアンス等を支援。最近は台湾有事も研究し企業を支援しています。
2. 会社解散か破産かM&Aか
B社の工場の製品は全て親会社のA社へ輸出していましたが、中国国内の人件費や原材料費の高騰、日本国内の市場の変化で次第に業績が下がり始め、ついには赤字に転落します。
B社は原材料の在庫管理、老朽化した工場の修繕工事の延期、残業の禁止、新規採用の中止などの方法で経費を抑える努力をしてきましたが経営状況は改善しません。営業許可の満了まであと5年でしたが、親会社のA社はB社を解散して清算することを検討しました。中国に進出して25年目、上海市から移転して15年目になります。
経営期間満了前に会社を解散する場合、従業員と労働契約を中途解約することの合意が必要になります。その合意を得るためには経済補償金がポイントです。計算式は労働契約法に従いますが、実際は10%~15%の上乗せは覚悟しなければなりません。
ところが、B社には従業員約1,000名分の経済補償金の内部留保がありませんでした。外資系企業の中国子会社では経済補償金が不足した場合、従業員は日本の本社からの送金を期待します。しかし、回収できない貸付金は健全な子会社管理ではありません。また税法上の制限もあります。そこでA社はB社に破産手続きを取らせることを検討しましたが、その場合、激しい労働争議が起きることを想定しなければなりません。B社にはそのような労働争議に耐える自信がありませんでした。
このようなとき、副総経理の父親からB社を買収して経営を引き継いでもよいという人を紹介されました(ここではY氏といいます)。Y氏は日本に留学経験がある中国人で日本語はネイティブに近く数字に強い人で、中国で幾つかの会社を経営しているということでした。Y氏の目的はB社が所有する国有地の使用権の取得です。X市にも住宅建設の波が押し寄せてきており、土地使用権の価格は高騰していました。Y氏は副総経理の父親から何らかの情報を得ていたのだと推測できましたが、我々日本人には窺い知ることはできず、また深く追求することは危険が伴います。中国では人脈と利権の複雑さが問題を解決することがあります。A社の取締役会はB社の持分の全部をY氏に譲渡することを決議し、Y氏と話し合いを始めることになりました。
3. 労働争議がおきる
A社とY氏は法的拘束力のない持分譲渡の意向書をかわし、Y氏はデューデリジェンスに着手しました。持分譲渡の話が譲渡契約の成立前に漏洩すれば従業員に不安感を与え何が起きるか分かりませんからデューデリジェンスは慎重に進められてきました。B社には日本語が分かる社員もいますので会社の中での会話にも注意が必要でした。
ある年の12月に我々は上海市の弁護士事務所でデューデリジェンスの結果を聞くために集まっていました。事業を継承するY氏のスタッフも参加していました。そのとき、B社に残っていた日本人の総経理から緊急の電話が入りました。既に夕方になっています。
総経理「従業員が家に帰らず会社の中庭に集まっています」
我々 「クリスマス前のイベントでもあるのですか」
総経理「三つの工場の従業員全員と管理部門の人間が幾つかのグループに分かれて何やら話し合っています。
従業員のリーダーらしい人が大きな声で怒鳴っています。A社が会社を売却したと怒っているようです」
持分譲渡の話が従業員に漏れたようです。あとで分かったことですが、日本人の総経理がB社創業以来の中国人の人事部長に話をしたようです。長い付き合いで信頼関係もあったので黙っていることが心苦しかったのでしょう。日本人の優しさが裏目に出た格好です。人事部長は携帯電話のSNSで工場長とライン長に知らせました。ライン長は部下に口頭で知らせるため工場の中庭で幾つかのグループに分かれて説明をしていたようです。残り二つの工場からもバイクや自転車で従業員が集まってきます。あっという間に中庭は集まった従業員で溢れてきました。
上海の会議室ではY氏が頭を抱え込んでしまいました。我々は会議を途中で切り上げ、夜のうちに移動し、その日はホテルで情報収集しましたが詳細は不明のまま。翌朝早くマザー工場に向かいました。既に工場の中庭には大勢の従業員が集まっており、誰ひとりとして作業に入る人はいません。管理棟には管理部門のスタッフが机の周りに固まっていましたが、全員の携帯のSNSで連絡が入ったらしく、一斉に中庭に黙って降りていきます。残りの二つの工場も同様で作業は止まっています。ここに至っては全てを説明しなければなりません。総経理が全員の前で、会社の株主は変わるが会社は経営を継続する、雇用は継続される、給料もいつものように支払われると、説明しました。おとなしく聞いてくれる人もおれば、わめき散らし人もいます。騒ぎは一向に収まる気配はありません。
4. 従業員代表大会
会社には工会(日本でいう労働組合)はありますが、中国の工会は会社と従業員との調整役という役目があるだけで従業員の利益を代表しません。その役目は従業員代表大会が負います。従業員表大会で数人の代表が選ばれます。B社の場合は工場長やライン長が代表になりました。従業員代表との話し合いは収拾がつかず、我々はホテルに帰ることもできないため管理棟の床に段ボールを敷いて横になりました。12月も後半、大変寒かったのを覚えています。段ボールは意外に暖かいということに気づきました。従業員代表大会では会社に対する要求が次々に出てきます。要求書は壁紙になって管理棟の壁に貼られます。食度の食事がまずい、とか関係なこともこの際一斉に出てきます。
我々はまず鎮政府から借りている二つの分公司工場から落ち着かせることにしました。それぞれ100名程度でしたのでそれぞれの代表と話し合いました。しかし誰も反応しません。従業員代表に一任しているようです。彼ら、彼女らは携帯電話のSNSを使って情報共有と意思統一を図っているようです。鎮政府にも説明するため訪問しましたが、工場の賃貸借契約は途中解約できないと筋違いの説明をされ、会社は継続しますと言っても「信用できない」と言われるばかりです。鎮政府とは普段も会食をしたりして仲良くしていたのでこのような反応は意外でした。ボタンの掛け違いで誰かのメンツを潰したようです。
このような冷たい反応はX市政府でも同じでした。マザー工場があるX市政府の労働局の職員が様子を見に来ていたので、改めて事態の説明をするためX市政府を訪問しました。すると1000名以上の工場の労働争議は2級都市のX市政府ではなく上位の1級都市の市政府で説明するようにと言われました。1級都市、2級都市というのは中国独特の行政区分で2級都市は1級都市によって管理監督されます。数十名程度の労働争議であれば2級都市が監督するが1000名規模になると1級都市が監督するようです。調べていると、この地方都市が所在する省政府から50名以上の労働争議は大規模労働争議とみなされ省政府と事前に相談するようにと言う省令が出ているようでした。事前に情報共有ができなかったためX市政府の担当者のメンツを潰したようです。このことが労働争議の状況を一変させる事態になりますが、それは後半に紹介します。
<筆者プロフィール>
大澤頼人(おおさわ・よりひと)
伊藤ハムにおいて約 30 年間企業法務に携わる中で、 1997 年から中国事業にかかわる。同社法務部長(2000 年~2013 年)、同社中国常駐代表機構一般代表(2002 年)、同社中国子会社の董事、監事等を経て、2013 年に J&C ドリームアソシエイツを設立し代表に就任。日本企業の中国ビジネスやグローバルガバナンス体制作りを支援している。同志社大学法学研究科非常勤講師(2006 年~2022 年)、立教大学法学部非常勤講師(2015 年)、上海交通大学客員教授(2008 年~2011 年)、中国哈爾濱市仲裁委員(2018 年~2023 年)、上場企業の社外監査役なども歴任。